1. 長期金利が2008年以来の高水準に ― 10年国債利回り一時1.8%
今週最も衝撃的だったのは新発10年国債利回りが1.8%に達したことです(Bloomberg)。
これはリーマン・ショック直後以来の高水準で、超長期ゾーン(20年・30年・40年債)ではイールドカーブのスティープ化が顕著に進んでいます。
背景にあるのは
- 円安による輸入インフレ再燃懸念
- 大規模経済対策に伴う国債発行増への警戒
- 海外金利(特に米10年債)の高止まり
長期金利が上がると、国の利払い費が増えるだけでなく、民間企業の借入コストも跳ね上がります。財政拡張を志向する政権にとって、これはまさに「自分で自分の首を絞める」状況になりかねません。
2. 円安が止まらない ― ドル円157円台前半へ
為替市場ではドル高・円売りが加速し、一時157円台前半まで円安が進みました。
主な要因
- 米利下げ観測の後退+Nvidia決算など米株好調
- 日本側の大規模補正予算による国債発行増懸念
- 日銀が追加利上げに慎重と見られていること
先日、日銀・財務省・経済財政担当相の三者会談が開催され、市場は「口先介入」の可能性を意識していますが、実際の為替介入はまだ見られていません。
3. 日銀は0.5%で据え置き ― でも市場は次の利上げを織り込み中
日銀は政策金利を0.5%で据え置きました。
しかし市場は、2026年にかけて追加利上げがあるという見方を強めており、2年国債利回りなどはすでに反応しています。
- IMFは「日本は2%インフレ目標を持続的に達成し得る」と評価
- 一方、UBSなどは「米国の関税リスクを考えると日銀は利上げしにくい」と指摘
日銀は「インフレvs景気」「財政リスクvs金融正常化」の狭間で、非常に難しいかじ取りを迫られています。
4. 高市政権の21.3兆円経済対策 ― 成長投資型だが財政懸念も根強い
高市内閣が打ち出した経済対策規模は事業規模で21.3兆円(財政支出は約13兆円程度)。
内容は
- 電気・ガス代補助
- 子育て世帯への現金給付
- お米クーポンなどの物価対策
- 半導体・AI・造船など成長分野への大型投資
短期的には家計支援+成長投資という「いいとこ取り」のように見えますが、財源はほぼ国債です。
市場は「また増税なしか?」「いつまでこれが続くのか?」と冷ややかで、長期金利上昇に直結しています。
5. 日本経済の中長期見通し ― 低成長+物価2%が基本シナリオ
大和総研の最新予測(第226回)では
- 2025年度実質GDP +0.7%
- 2026年度 +0.8%
賃金上昇と価格転嫁が進むことを前提に、消費者物価は「+2%程度」で推移する見通し。
IMFも同様に「2%インフレの持続的達成は可能」との見解を示しています。
ただし、下振れリスクとして
- 財政債務の膨張
- 米国の対中・対日関税強化
- 円安による輸入インフレの悪循環
が常に意識されています。
投資家が今考えるべきこと
- 金利敏感資産は要注意
債券、J-REIT、高配当株、不動産などはポジションを見直す時期です。 - 円安ヘッジを再検討
海外資産比率が高い人は為替ヘッジ付き投信や、ドル建て資産の積み増しを検討する価値あり。 - 成長セクターはむしろチャンス
政府が本気で金を突っ込む半導体・AI・防衛関連・造船などは、中長期で面白い可能性があります。 - 政策ウォッチが最重要
補正予算の本格編成(12月)、日銀金融政策決定会合、為替介入の有無――これらを逃さずチェック。
まとめ:日本は「財政と金融の綱引き」の正念場
現在の日本は
大規模財政出動 ↔ 長期金利上昇・円安 ↔ 日銀の正常化意欲
という三すくみ状態にあります。
短期的にはボラティリティが高く、痛みを伴う調整が続くでしょう。
しかし賃金上昇と成長投資が着実になされれば、「失われた30年」からの本格的な脱却も夢ではありません。
投資家としては
「リスクをしっかり管理しながら、成長テーマを逃さない」
というバランス感覚が今、最も問われていると思います。
引き続き、政府・日銀の動きと国債・為替市場の反応を注視していきましょう。

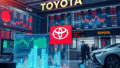

コメント